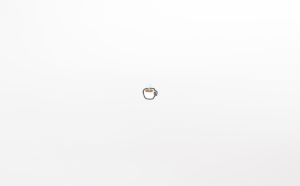日本の大人
渋谷に行く用事があり、自宅近くから渋谷行きのバスに乗った。
渋滞にさしかかると到着時間がずれるけれど、バスは乗り換えなくていいし、ゆったりと景色を眺められるから好きだ。だけどその日はあと少しで読み終える本があったので、席に座ってすぐにページをめくった。
それは1940年代に上海で暮らしていた日本人の青年の日記だ。太平洋戦争が激化しているなか、彼は軍事関連の仕事で上海に赴任し、その地で終戦を迎える。日記には当時の街の様子や知識人同士の交流、そしてこんな状況下、いや、そうした状況下だったからなのか、みちならぬ恋におちていく様子が描かれていた。
その文章はどこも深い教養と観察眼にあふれていて、引き込まれるようにして読んだ。そしてこの日記を書いた当時、著者が27歳だったと知ってため息が出た。自分が同じ年のとき、何を書いていただろうか? もし日記を書いていたとして、こんなに深いことが書けただろうか? おそらく書けないと思う。
そのとき「10年、幼い」という言葉を思い出した。
数年前に、ある大学の経済学系の先生を取材する仕事を請けた。その先生の授業やゼミの様子を誌面でレポートし、さらに先生からインタビューをいただくという内容だった。
すべての取材を終えて別れの挨拶に伺うと、先生がお茶をいれてくださった。
かなりの高齢だったが身のこなしは軽く、自分のことを『僕』という人だった。歯切れが良くて語尾が軽やかな話し方はモダンで、生粋の東京人という印象を受けた。
お茶を飲みながら話をしていたら、何かの折に先生がぽつりと言った。
「今の大学生の意識は、昔に較べて10年ほど幼いのです」
そこは新興の大学で、これから知名度を上げていこうとしているところだった。しかし先生はこの学校に来る前に教えていた名門大学でもそう感じていたのだという。
昔とはどれぐらい前かと聞くと、少し考えて、10年、15年前の学生はまだギリギリで大人だったように思うとおっしゃった。
2011年の今だと、20年から25年ぐらい前の学生たちといったところだ。
軽い気持ちでたずねた。
「そうしますと……今の28歳が昔の18歳という感じですか?」
そうです、と先生はうなずいた。
何か理由があるのだろうか、と聞いた。
すると、昔は高校や短大を出て社会に出る人が多く、同年代ですでに稼いでいる人達が大勢いた。だから大学生は自分たちがモラトリアムであることを自覚していたし、4年間も学べるのは恵まれたことだという意識がどこかにあったからだ──そんな感じのことを一気におっしゃって先生は小さく笑った。
「苦学生なんて言葉、もう死語でしょうね」
「あまり聞きません」
「昭和の時代に学費を自分で作りながら学んでいた生徒は、人への接し方も話し方も今の30代ぐらいの感じでしたよ」
そうしたわけだから、と先生は続けた。
「今の18歳は昔の8歳ぐらいだと僕は思っています。だから算数を教えるのも仕方がないのです」
その先生のゼミはまず数学の初歩を教えてから、専門分野に進むというのが特色だった。
この大学の入試には数学がないので、学生達は数学の基本的なことを忘れ、あるいはあまり学ばずに大学に入ってくる。算数のレベルで戸惑ってしまう学生も少なからずいて、今さらそれを人にも聞けず、やがてゼミにも講義にも来なくなってしまうらしい。
最近ではこうした数学の基礎を学ぶ機会を設けている所もあると聞くけれど、当時はそれほどなかったように思う。
10歳、幼い。
そう言って先生は強い口調で続けた。
「幼いから素直で純粋です。だからたやすく心が傷ついてしまう。そう思って僕は指導方法や言葉もとても考えながら指導しています」
ああ、されど……。
先生の話を聞きながら、ぼんやりと思った。
笛吹けど踊らず……。
教え子たちに取材をしたのだが、先生の配慮はあまり伝わっていないようだった。みんなサークルやアルバイトに関しては楽しげに語ってくれるのだが、肝心の授業の話になると口が重い。今さら数学の勉強をするより、アルバイトやサークルで実績を積んだ方が人間性や視野が広がる──そうした意見を持っている学生もいた。
どこか釈然としない思いを感じた。そして『10年、幼い』という言葉が心に残った。
しかし2011年の今、昔の日本人の日記に接してみると、10年幼いのは、あのときの学生ばかりではなく、私自身もそうであったことに気付く。終戦時に20代後半だった青年の文章は、今の30代後半、40代前半のような成熟度があった。
そう思って本を閉じたら、バスに二人の年配の男性が乗り込んできた。
年のころは70代ぐらい。久しぶりに会った仲らしく、話がはずんでいる。一人は粋な白い帽子、もう一人はパナマ帽をかぶっていて、互いに自分のことを僕、と言っていた。大きな声だったけれど、その話し方は軽やかで心地よく、『10年、幼い』と言ったあの先生の口調を思い出した。
二人は車内を見渡しながら歩いてきて、私の前に座った。そして白い帽子の人が終戦直後に上野駅についたときの話をした。話の詳細はわからないけれど、あたり一面の焼け野原を見て呆然とした、と言っている。
「みんな焼き払われて、町のはるか向こうにぱーっと海が……海の……水平線が見えたよ。あの光景は忘れられん」
「僕もおんなじようなものを見た」
パナマ帽の老人がうなずきながら言った。
「裏山から見たらぱーっとね……。あんな焼け野原……」
一瞬、黙ったが、だからさ、とパナマ帽が言葉を続けた。
「東北だって、すぐに復興するよ。だって僕らは日本人だもの」
一瞬、違和感を感じた。被災地から離れた東京で、そんなことを気楽に言っていいものだろうか。そう思ったけれど少し考え直した。終戦後、焼け野原だった日本を復興させたのは、この人達の世代だ。
パナマ帽が窓の外のビル群を指さした。
「あんな状況からこんなになったんだよ、ほら、ほら」
「そうだね」
穏やかにうなずき、白い帽子の老人が窓の外を見た。
その様子に“上野駅についたら驚いた”と、彼が話していたのを思い出した。
電車が上野に着いたら驚いたということは、東北から上京した人かもしれない。西から上京した人は新橋、品川、東京駅あたりで焼け野原に気付くのではないだろうか。
二人とも東京の人に思えるけれど、ひょっとしたらこの白帽の人は東北の出身か、東北に疎開をしていた人かもしれない。年代的に見て、二人とも終戦時は子どもだったような気がする。
そう思ったとき、そうだよ、と力強く白帽がうなずいた。
「そうだよ、できるさ」
できるよ、とパナマ帽が続けた。
「やれるさ。そんときまで僕らが生きてるかどうかは、わかんないけど」
二人は笑った。それから話は別のことに移った。
膝の上に置いた本をバッグに入れながら、新聞で読んだ東北の方の言葉を思い出した。
避難所で数日過ごして外に出たら、町の向こうに水平線が広がるのを見たと、その方は言っていた。本来なら見えるはずがない場所なのに、建物が押し流されてしまったから、はるか彼方の水平線まで見えたという。
目の前の年配の方々が子どもの頃に見た光景と同じ事が今、東北のいろいろな町にある。そしてそのさまは戦後66年たって大人になっても、声を詰まらせるほどの衝撃として残っている。一体どれほど多くの子どもたちが今、水平線を眺めて暮らしているのだろう。
東北の復興はすぐだと目の前の二人は言った。その理由が“だって、僕らは日本人だもの”。
なんて根拠のない言葉だ。しかも終戦直後の日本人ほど、おそらく私たちは剛毅ではない。10年幼いのは学生ばかりではなく、大人もおそらく、あの時代の人々より幼いのだ。
だけど、できるさ、と力強く言った彼らの言葉が耳に残った。その一言は自分たちより若い世代を信頼している力に満ちていた。
バスは渋谷に着き、二人は楽しそうに話し続けながらバスを降りた。そしてこれから何をしにいくのか、意気軒昂に肩を並べて歩いていく。夏の日差しのなかで粋なパナマ帽と白帽が二つ。逆方向へと歩き出しながら、先ほどの言葉をかみしめた。
できるさ。きっとやれるさ。
今の日本が嫌だからと言って逃げる場所もないし、逃げるわけにもいかない。何がおきたか、それからどうなったのか、それを忘れずに道を模索
していくしかない。個人ができることはささやかだとしても、それは今も昔もおそらく変わりない。それぞれがそれぞれの場所で少しずつ積み重ねていったものの集大成が、きっと未来につながるのだろう。
10年幼くても頼りなくても、それをするのはあらゆる世代の今、ここにいる大人がやるしかない。水平線を眺めて暮らしている子どもたちが、安心して大人になれるように。
振り返ったら、もう帽子は見えなかった。
時間にして数分、鮮やかな印象だけを残して、66年前に少年だった二人は渋谷の雑踏のなかに消えていった。
伊吹有喜